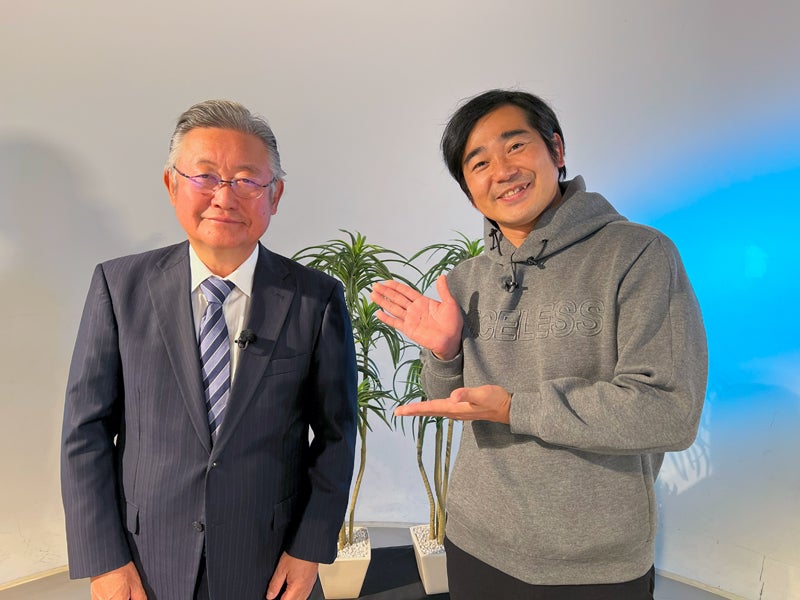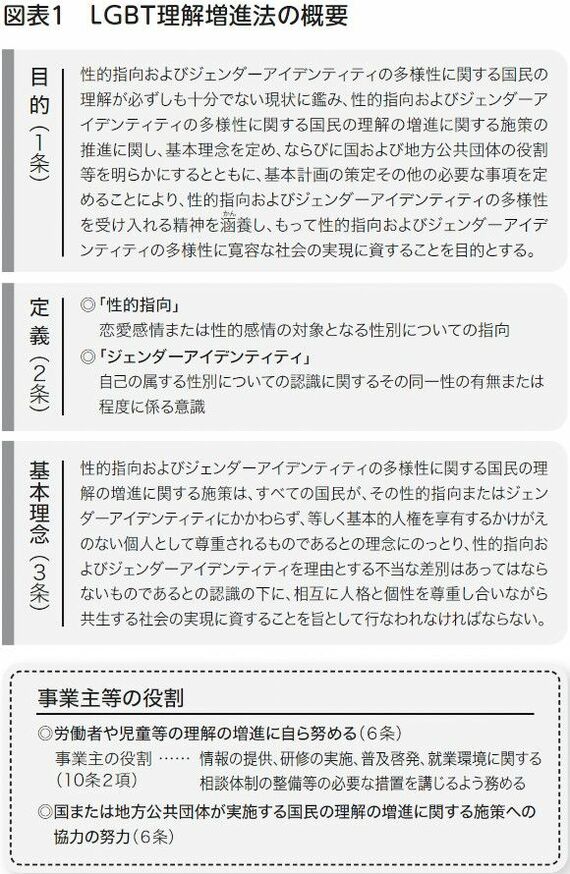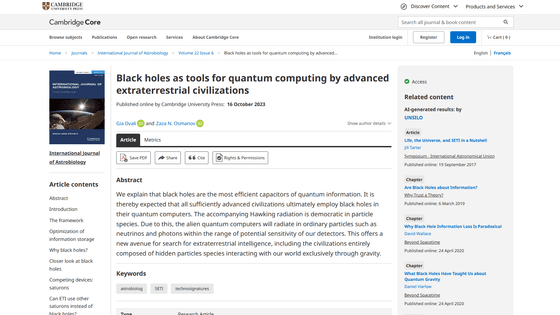- 社会学研究科講師後藤 伸彦
CHAT IN THE DEN
2023年12月27日 掲載
葛藤をキーワードにした集団間関係の研究からスタート
私の研究領域は社会心理学、社会的認知、消費者行動です。集団への所属が人の感情、態度、行動、認知機能、人生満足感などに与える影響について興味を持って研究を進めています。
大学院生の頃は、主に集団間葛藤について研究をしていました。社会心理学には、他者や集団に対する人の認知の仕方を研究する「社会的認知」という領域があります。さらにそのカテゴリ内にある、集団にフォーカスした集団間関係という領域において、葛藤や罪悪感をキーワードに私の研究者人生はスタートしました。
英語ではよく「Us/Them」という表現を用いますが、人には自分と他者を分ける傾向があります。そのような分け方をする一方で、人は自分が所属する集団内で他者が行った行為について罪悪感を覚えることがあります。また、相対する集団の誰かが行った行為に対しても、「その集団の成員全体が罪悪感を覚えて欲しい」と期待することがあります。自分と他者をある時は同一のものとして、ある時は異質なものとして認知するプロセスで、個人の葛藤が集団間の葛藤に発展してしまうケースも珍しくありません。しかし見方を変えれば、そのような認知の理解が集団間の葛藤の解決にもつながるのではないか。国と国、民族と民族の衝突の原因でもあり、解決策でもある。集団間葛藤の研究に、そのような可能性を感じたのです。
現在はさらに研究を推し進め、複数の集団への所属によって個人の認知機能や実行機能にどのような変化があるのか、ウェルビーイングにどのように寄与するかについて調べています。こちらの研究については後ほど紹介しましょう。
自分と同じ「人」が、何故紛争の当事者や被害者になるのか
私は子どもの頃から、国と国が何故いがみ合うのか、ということに関心を持っていました。きちんと考証したわけではありませんが、私が生まれた1984年以降は、紛争の勃発や収束が増え始めた時代という印象があります。親に連れられてロバート・キャパの写真展に行き、紛争や戦争の現場を写真を通じて垣間見ていた私は、「何故こうなるのか?」と疑問に感じていたのです。
特に私が関心を寄せたのは、そこに写っていた「人」です。自分と何も変わらない人たちが、何故紛争や戦争を引き起こす当事者になったり、被害者になったりしてしまうのか。高校のときに『ホテル・ルワンダ』を観たのですが、この映画も私の中に深い疑問を残しました。それまで仲良くしていた民族同士が仲違いし、とうとう殺し合いを始めてしまうストーリーに、「何故こうなるのか?」という思いを強くしたのです。
一方、子どもの頃から語学に関心を持ち、積極的に英語を学んでいた私は、高校の英語の先生からアメリカへの進学を勧められました。先生が紹介してくれた大学は、2001年設置という新しい大学です。「大学の歴史づくりに参加してみたくはないか?」。そう背中を押されて、私はアメリカに渡りました。
心理学には、紛争や戦争の解決の一助になる可能性がある
アメリカの大学に入ってからも、「何故いがみ合うのか」という疑問は残ったままでした。経済学、宗教学、国際関係学......大学にはさまざまな授業があります。歴史ある学問がそれぞれの領域で紛争や戦争の解決に取り組んできたはずなのに、何故なくならないのか。その疑問を抱えたまま、大学での日々を過ごしていました。
もっとも、成績は決して良いほうではなかったです。周りは大学院進学を志望する友人ばかりでしたので、自分も大学院に行くことになるだろうと軽く考えていました。しかし成績がついてきそうにありません。日本に戻って就職活動をしたほうがいいだろうか......。漠然とした不安を感じながら大学の図書館に行ったとき、その後の私の人生を方向付ける本に出会ったのです。それはポジティブ心理学の大家であるマーティン・セリグマン教授が編纂した本でした。セリグマンがアメリカ心理学会の会長を務めていた頃、クロアチア心理学会からの打診をきっかけとして書かれたものです。20世紀において大量虐殺が起きてしまったケース/起きなかったケースを比較し、21世紀に向けて民族政治紛争を回避するために、心理学にできるアプローチが紹介されていました。「心理学が、紛争や戦争の解決の一助になるのか」。子どもの頃からの疑問に光が差した思いでした。読み終えた私は、心理学の研究者への道を進もうと決めました。
心理学の授業を担当していた先生の計らいで、近くにあるUCLAの特別授業に参加。登壇していた社会心理学の大家であるバーナード・ワイナー教授から、同教授が家族ぐるみで付き合っていた唐沢穣教授(名古屋大学)の存在を教えてもらいました。そこで私は帰国後、唐沢教授の研究室に入ります。当時研究していたのが、はじめに紹介した集団間葛藤です。それから数年後、ルワンダの研究者が書いたルワンダの大虐殺に関する論文の中で、私の論文を引用してくれたことがありました。子どもの頃からの疑問に対する私の考えが、研究の道を志すきっかけとなった遠く離れた地の研究者のヒントとなったことに、深い感動と感謝を覚えました。
集団ごとに「私」が切り替わると、認知機能・実行機能が向上する
集団間関係の葛藤や罪悪感の研究は、もちろん今も続けています。ただ、ここ数年の間に、私の関心が「人は集団に所属することでどのような影響を受けるのか」にスライドしていることに気づきました。表向きには「集団間葛藤ってヘヴィーなテーマだから明るい話をしたくて」と言うことにしていますが。そもそも人は、ただ一つの集団に属しているわけではなく、出身地、会社や学校などの組織、住んでいる地域、家庭......と、さまざまな集団に属しています。これほど多くの集団に所属し、その集団ごとに自己を定義する動物が人以外にいるでしょうか。特定の集団に属しているときに人が受ける影響よりも、集団に属することで人はどのような、特にポジティブな影響を受けるのかについて、研究を深めてみたくなったのです。
具体的には、これもはじめに紹介したように、より多くの集団への所属が人の認知機能・実行機能にどう影響するか、そしてウェルビーイングにどのように寄与するかを調べる研究です。現段階では、所属する集団が多ければ多いほど、人の認知機能・実行機能は向上していくという仮説を裏付ける実証研究を行っています。
さまざま集団に所属することは、集団の数だけ「私」を持ち、頭の中で切り替えて行動していることになるはずです。集団Aではこのように振る舞おう、集団Bでは言葉遣いに気をつけよう、友人との集まりではこうしよう......この自己の切り替えが脳を刺激し、さまざまな集団に所属することで社会的自己が増え、認知機能・実行機能が高まると考えます。逆に言うと、どの集団に所属しても頑固に自分のスタイルを貫く人は、認知機能・実行機能があるレベルから上がらないかもしれません。
今までに、毎回400名ほどの方々に協力してもらい、記憶と切り替えに関する実験を実施し、複数の集団への所属~認知機能・実行機能の高まりという相関が見えてきました。
一橋大学は研究でも授業からもインプットが増やせる恵まれた環境
教員として学生に教える側になって感じるのは、日本における心理学が、臨床心理学と認識される傾向があるということです。心に病を抱えている人をどう寛解させるか、というテーマ自体は重要ですが、心理学が扱う領域はそれだけではありません。アメリカでは心理学が「実証科学」として受け入れられていて、個人の経験則を離れたマーケティングなど、実社会でも活用されています。
このようなギャップを埋める必要性を感じてはいますが、それとは別に一橋大学の学生とは「一緒に研究を掘り下げられる」手応えを感じられるのが嬉しいですね。たとえば書籍の輪読では、私が1週間かけて準備をしておかなくても、授業やゼミで一緒に内容を噛み砕いていけばいいのです。おかげで私個人の情報のインプットも、授業やゼミからのインプットも増えました。ですからこれからも研究を推し進められますし、学生の皆さんと実のあるコミュニケーションをとることもできる。この環境にはとても感謝しています。(談)
からの記事と詳細 ( さまざまな集団への所属が、人にどのような影響をもたらすか | 研究室訪問 - 一橋大学 )
https://ift.tt/QSUFVjN