1999年、茨城県つくば市のNEC筑波研究所で世界初の技術が産声を上げた。超電導回路を使った「量子ビット」の製造に成功したのだ。
それから20年あまりたつが、NECから量子コンピューターが生まれたという話は聞かない。今はどうなっているのだろうか。
NECセキュアシステムプラットフォーム研究所の白根昌之・量子コンピューティング研究グループ長は「2年前の2020年に筑波研究所は閉鎖した」と話す。量子ビットの製造成功は大きな第一歩だったが、基礎技術レベルのもの。「量子ビットを動かすことはできたが、動作する時間は非常に短いものだった」(白根氏)。実用に耐えるレベルまでもっていくには長い年月が必要となった。その過程で、予算規模で勝る米中勢に追い抜かれてしまったのだ。
白根氏は今、同じつくば市の国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)に19年に設置された「NEC-産総研量子活用テクノロジー連携研究ラボ」での勤務も多い。同ラボの責任者を兼務しているからだ。開発を進めているのは、組み合わせ最適化問題を解くのに特化した「量子アニーリング方式」の量子コンピューター。産総研や東京工業大学、早稲田大学、横浜国立大学などと共同で、23年の実用化を目指しているという。
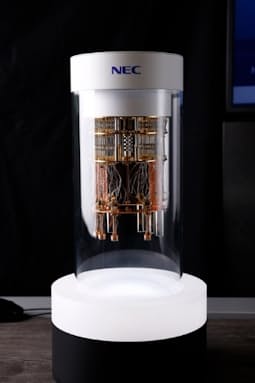

米中が実用化に向けた開発にしのぎを削るのは、幅広い用途に使える「量子ゲート方式」の量子コンピューターだ。NECがあえて違う方式を選択したのは、事業性を重視しているため。白根氏は「量子ゲート方式はまだエラーの発生が多く、実用化までは20~30年かかるだろう。ここ5~10年の間は、量子アニーリング方式のほうが事業化しやすい」とみる。
事実、カナダのベンチャー企業であるDウエーブ・システムズは量子アニーリング方式の量子コンピューターを商用提供済みだ。NECは20年、Dウエーブに1000万ドルを投資し、21年からはDウエーブの量子コンピューターをクラウド経由で使えるサービスの販売を始めている。
そしてNECは「疑似アニーリング」というソフトウエア技術も持っている。これは、量子アニーリング方式を半導体を使った従来のコンピューターで再現するもの。NECが21年からクラウド提供を始めた「ベクトルアニーリング」は同社のベクトル型スーパーコンピューター「SX-Aurora TSUBASA」上で動作する。

NECは傘下の物流会社で、配送効率化にこの技術を活用。人手で2時間かけていた配送計画の構築がたった12分で完了し、効率的なルート選定で配送コストを最大3割程度下げられることが確認できたという。
22年4月には「量子コンピューティング事業統括部」を新設し、本格的なビジネス展開に乗り出している。同部長の泓(ふち)宏優氏は「量子ゲート方式に取り組んでいないからダメだとは考えていない。人工知能(AI)であれ、量子アニーリング方式であれ、顧客の課題解決に最適な手段を提案することが我々の役割だからだ」と力説する。
富士通は量子ゲート方式に触手
疑似アニーリングは日立製作所、東芝など国内勢がこぞって力を入れており、富士通も「デジタルアニーラ」の名称で18年から提供を開始している。契約数は国内131件、海外55件となっており、実際に通信ネットワークの最適化、半導体材料の最適配合探索などでの活用事例が出ている。研究本部の富士通研究所で量子研究所長を務める佐藤信太郎氏は、「どんな問題が解けて、どんな問題は解けないのか、ノウハウが積み上がってきている。量子コンピューターの実用化に向けたソフトウエア開発に役立つ」と話す。
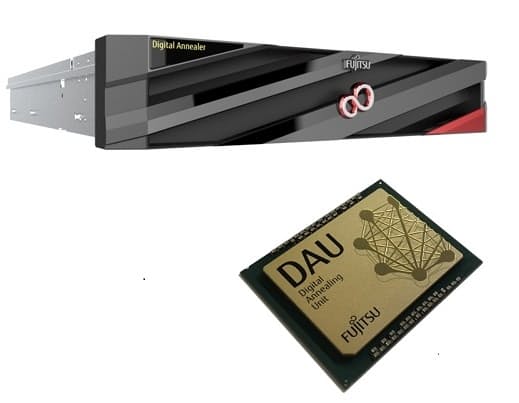
それに加えて、富士通は量子ゲート方式のシミュレーションマシンも開発。スパコン「富岳」向けのプロセッサーを使い、36量子ビットの量子回路の動作を再現できる世界最速のシミュレーターを22年3月に開発した。目下、世界的な半導体不足で遅れが生じているものの、9月には39量子ビット、年度内には40量子ビットまで再現できるよう処理能力を上げる予定。富士フイルムと材料設計の量子アプリケーションの共同開発も行う。

富士通はNECと異なり、量子ゲート方式の実機開発をターゲットに据えている。21年4月、国立研究開発法人 理化学研究所(理研)の量子コンピュータ研究センター(RQC)内に「理研RQC-富士通連携センター」を開設した。理研は、1999年に世界で初めて量子ビットの製造を成功させた元NECの中村泰信氏と蔡兆申(ツァイ・ズァオシェン)氏が所属する、日本の量子コンピューターの中核開発拠点だ。
理研は22年度中に国産第1号の超電導回路を用いた量子コンピューターを完成させる予定だが、富士通が共同開発する実機は23年度の完成を見込む。100量子ビット以下の規模というので、米IBMが21年に開発した最新鋭機(127量子ビット)には及ばない。
ただし、学術研究の視点が強い理研の取り組みにメーカーである富士通が関わることは、今後の実用化を占ううえで重要だ。富士通の佐藤氏は「量子ビットの大規模化を実現するためには、均質な量子ビットの製造や実装が必要。ユーザーが使えるレベルにするには、企業の視点が欠かせない」と話す。富士通にとっても、量子ソフトウエア開発において、実機を持つことは重要性は増している。
さらに富士通は、理研との共同開発だけでなく、20年からオランダのデルフト工科大学とも共同研究を進めている。こちらは超電導ではなく、ダイヤモンドの中にある錫(すず)などの不純物が量子ビットになる「ダイヤモンドスピン」を用いる。佐藤氏は、「4~5年では90量子ビット程度にとどまるだろうが、その後大規模化を目指したい」と意気込む。

鍵を握るのは「大規模化」
現在、量子コンピューターで主流となっている超電導回路と比べると、自然界にある原子を使うため、制御は難しいという。それでも着目するのには理由がある。
まず、超電導回路は絶対零度(セ氏マイナス273.15度)近くまで冷却する必要があるが、ダイヤモンドスピンはマイナス269度で済む。超電導方式よりも4度高いだけだが、冷却装置の能力は10万分の1でよい。加えて量子ビットも小さいため、超電導方式よりも小型化に有利という。
また量子ビット間を光でつなぐため、「超電導回路よりも安定的に大規模化が可能」と佐藤氏はみる。
現在の技術では、量子ビットのエラーを訂正して計算結果の精度を上げるためには今のところ100万量子ビット以上まで大規模化する必要があるとされる。「超電導回路で実現しようとするとサイズが巨大になり、コストも1兆円くらいかかるだろう」(佐藤氏)。何らかの技術的なブレークスルーがなければ実用化は困難という。その一つの候補がダイヤモンドスピンというわけだ。
「富士通にはハードウエア実装やソフトウエアのノウハウがあり、量子ビットの技術以外は全て持っている」(佐藤氏)。超電導回路が本命かどうかも分からない以上、現段階で実機があるかどうかは決定的な差にはならないと話す。来るべき「量子の世紀」へ向け、量子ビットの技術に強みを持つ研究機関と組み、ゲームチェンジを狙う。
(日経ビジネス 佐藤嘉彦、中西舞子)
[日経ビジネス電子版 2022年6月22日の記事を再構成]
からの記事と詳細 ( 量子コンピューター開発競争 諦めないNECと富士通 - 日本経済新聞 )
https://ift.tt/0GrdWno


No comments:
Post a Comment